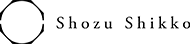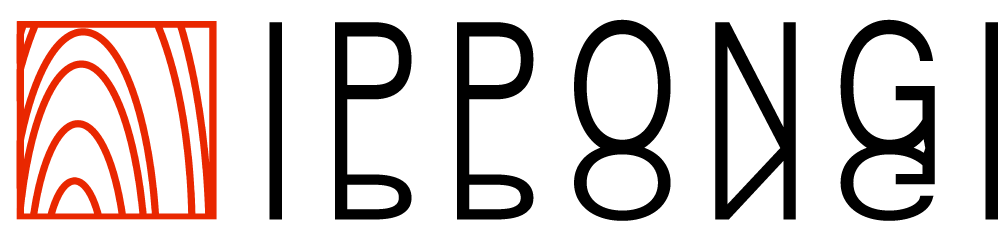
匠頭漆工一同
①一本樹:一本の“木”から切り出した木という自然そのものの魅力、そしてその力強い美しさを引き出す技術との融合を魅せる
②一本気:純粋で混じりけのない自然の尊さを一途に伝えていこうとする心持
point 1: 五感で楽しむ
point 2: 組み合わせは30通り
point 3: お手入れは簡単に
五種の雄

深緋
KOKIHI
たっぷりのボウルで香りと余韻をお楽しみ頂ける深緋(こきひ)。ボルドーに代表される、カベルネ・ソーヴィニョンやメルローを基準に熟し枯れたワインを楽しんで頂くのがおすすめです。 「深緋といふは緋の色甚深くして黒くなりたるをいふ。たとへば桑の実の、初は赤きが、後黒となりたるが如しといへり」これは明治時代の『歴世服飾考』の中の言葉。深緋とは、紫みの暗い赤色で、茜と紫とで染めたもの。名称にある緋の色感はなく黒みの強い色です。飛鳥や奈良時代までさかのぼると役人の装束の色として使用されていたほど、非常に重要な高貴な色合いです。是非お飲物とリンクさせてあげてください。

紅鳶
BENITOBI
見ていてうっとりするような繊細な曲線美とふわっと膨らんだボウル部分が特徴。ブルゴーニュに代表されるピノ・ワールやイタリア・バローロに代表されるネッビオーロのような少し茶褐色によった繊細でエレガントな色合いのワインに是非。奥行きと深みのある味わいを更に器が引き出します。丁度良いサイズ感なので、アイスコーヒーや和酒など様々な遊びのある飲み方もおすすめです。鳶の名がついた色。力強さと美しさを共に兼ね備えた優雅な姿を名前に投影しています。

紺瑠璃
KONRURI
毎日の食卓に登場させたいシンプルで優雅な佇まいと、すっぽりと手に収まる安心感が共存する愛らしい紺瑠璃。ワインは勿論のこと、飲物全般にお使いいただけるので敢えて特定の飲物を連想させないような名前を付けました。共に歩むパートナーによって様々なアイデアが生まれるようなそんな器です。瑠璃色は仏教において珍重された七つの宝「七宝」にあげられる青色の宝石であり、古代から珍重されています。この器も人々のスタンダードとなり、日々の宝として、長く愛されるものとなりますように。

瓶覗
KAMENOZOKI

裏葉
URAHA
木を愉しむ

欅
けやき

檜
ひのき

水目
みずめ

桜
さくら

栃
とち