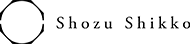「木地師の現場へ!職人専門用語集。」
皆さま大変ご無沙汰してしまい恐縮です。久しぶりにOtaku記事投稿です。
今回は初心に返って?工場で日々飛び交う職人たちの専門用語を集めてみました。
木地師の歴史は古く、その起源は9世紀まで遡ります。伝統工芸の業界では、昔からの単語が未だに使わているのはよくあること。どれぐらいの単語を当時のまま今も使っているのか、考えるだけでも少しワクワクしますね。

⚫︎ 木地師の職人専門用語集 ⚫︎
用語集に入る前に基本的な木地加工の工程をおさらい。
荒挽木地仕入→乾燥→面取り→外挽き→(中挽き)→内挽き→検品
この全木地加工工程の後に、「塗り」の工程が入ります!
ご覧いただいた通り、木地挽きといっても一言では表せないほと沢山の工程があるんです。それでは、私たち木地師職人の専門用語たちをどうぞ。
荒挽き

荒挽き木材の最初の粗削り工程であり、後の仕上げ加工や乾燥を考慮した重要なプロセス。丸太から必要な形状に荒く加工する。基本的な加工方法は旋盤加工(挽き物)で、木地師同様木材を回転させながら刃物で荒く削り出す。精密な仕上げはせず、後の加工に備えて余裕を持たせた寸法で加工。
木地挽き

木地挽き旋盤(もしくはろくろ)を使って木材を削り、器の形を作る技術・工程。荒挽き屋から受け取った木材を、木地の状態や天候を考慮しながら水分量10%以下まで乾燥させ、旋盤(ろくろ)で挽き上げる。加飾挽きといわれる細かい模様や、表面の仕上げは手作業で行い、塗り手前の最終の形までもっていく。
面取り



面取り木地における面取りは、乾燥の後の木地挽き最初の工程。全ての器に必要な工程ではなく、荒挽き木地と作りたい器の完成形の高さが異なる場合、上部(面部分)を削り落とすこと。写真はビフォーアフター。
外挽き

お椀やカップなど基本的な器の成形はは大きく分けて外挽きと内挽きの2工程に分かれる。外挽きは木材の外側を独自の刃物を使用し、木地を回転させながら削り上げ成形する技法。
内挽き

木地挽きの成形は大きく分けて内挽きと外挽きの2工程に分かれる。外挽きと対になり、文字通り木地の内側を削り成形する技法。内挽きは、外挽きより高度な技術が必要。ふちの薄さもこの工程で決まる。
白木地

白木地は、漆やガラスコーティングなど最終の塗装や仕上げを施す前の「素の木地」の状態を指す。漆器や工芸品の一番土台となるもの。白木地自体は木の肌部分が空気に直接触れている状態なので、吸湿性が高く、経年変化しやすいため湿気や油分など取り扱いには注意が必要。「白木」というのは木地が削りたての状態だと表面が明るい木の色をしているために「白」木と呼ばれたらしい。
塗り

木地挽き後の工程。塗りの中には下地塗りから、漆塗り、ガラスコーティングなど様々な塗り方法がある。この塗りを施すことで、日常にも使える強い器となる。ちなみに塗りをする伝統工芸士のことを塗師というが、読みかたはぬし。
匠頭漆工ではガラスコーティグの塗りを自社で施しています。ガラスコーティングについて詳しくはこちら▶︎
ペーパーかける


外挽きの後に紙やすりで仕上げをすることを、ペーパーをかけるという。旋盤で挽かれた木地に、手作業で表面全体に微妙な調整を行いながら仕上げを施す。
刃物

木地加工の轆轤旋盤で固定して使用される刃物は全て手作り。夫々の器に応じて、完成バイトと呼ばれる棒状のハイス(高速度鋼)を加工して作る。IPPONGIなど挽き上げる工程が多い器だと、それぞれの工程に専門の刃物が必要になるため数も膨大になる。刃物の切れ味が出来上がりを大きく左右するので、職人が一番神経を使う工程の一つ。少しでもくるっていると美しい器は出来ない。
節

樹木が成長する過程で枝が生え、それが幹に埋まることでできるのが節の部分。節の種類は3つあり、しっかりと木目と結びついていて抜け落ちることがない=強度が保たれる「生き節」、既に枯れた枝の痕跡が残り、乾燥などの過程で抜けおちることがあるため補修等が必要となる「死に節」、そして節が完全に抜け落ちて穴があいた状態の「抜け節」。*現在まで漆器産業においての「節」は加工し辛く、見た目も不揃いのため廃棄されていた。私たち匠頭漆工はこの「節」に改めてスポットライトを当てたmebukiというシリーズを展開しています。mebuki シリーズはこちら▶︎
型

外挽きをするために必要なアクリル板で出来た型。器の最終形を丁寧に元に手作業で作られたもので、この型に合わせて刃物が自動で動き外挽きの加工をしていく。
ハメ

内挽きをするために木地を固定する木製のもの。器の形にぴったりと合わせて作られており、このハメが確実でないと内挽きもうまく行うことができない。
セットする

セット旋盤を挽きたい器に合わせて調整すること。刃物やハメなど工程によって必要なものが異なるため、工程の種類が多いほど時間がかかる。
寸 / さぶろく・さんなな・さんぱち

3.6寸、3.7寸、3.8寸のお椀のこと。漆器業界ではいまだに割と「寸」の単位を使う。
例:「さぶろくのけやき、まだ在庫あったっけ?」
うちで一番注文が多い、いわゆる一般的な大きさのお椀は3.8寸(直径11.5cmほどのもの)。ちなみに寸は中国が起源で、元々指の幅を表す単位。日本では江戸時代に1寸を約3.03cmと定義。(故に一寸法師は3cmほど!)
今回は一先ずこの辺りで。他にも、たくさん用語があるので、さらにOtakuっぽさを増したラインナップで後日お届けします、お楽しみに♪